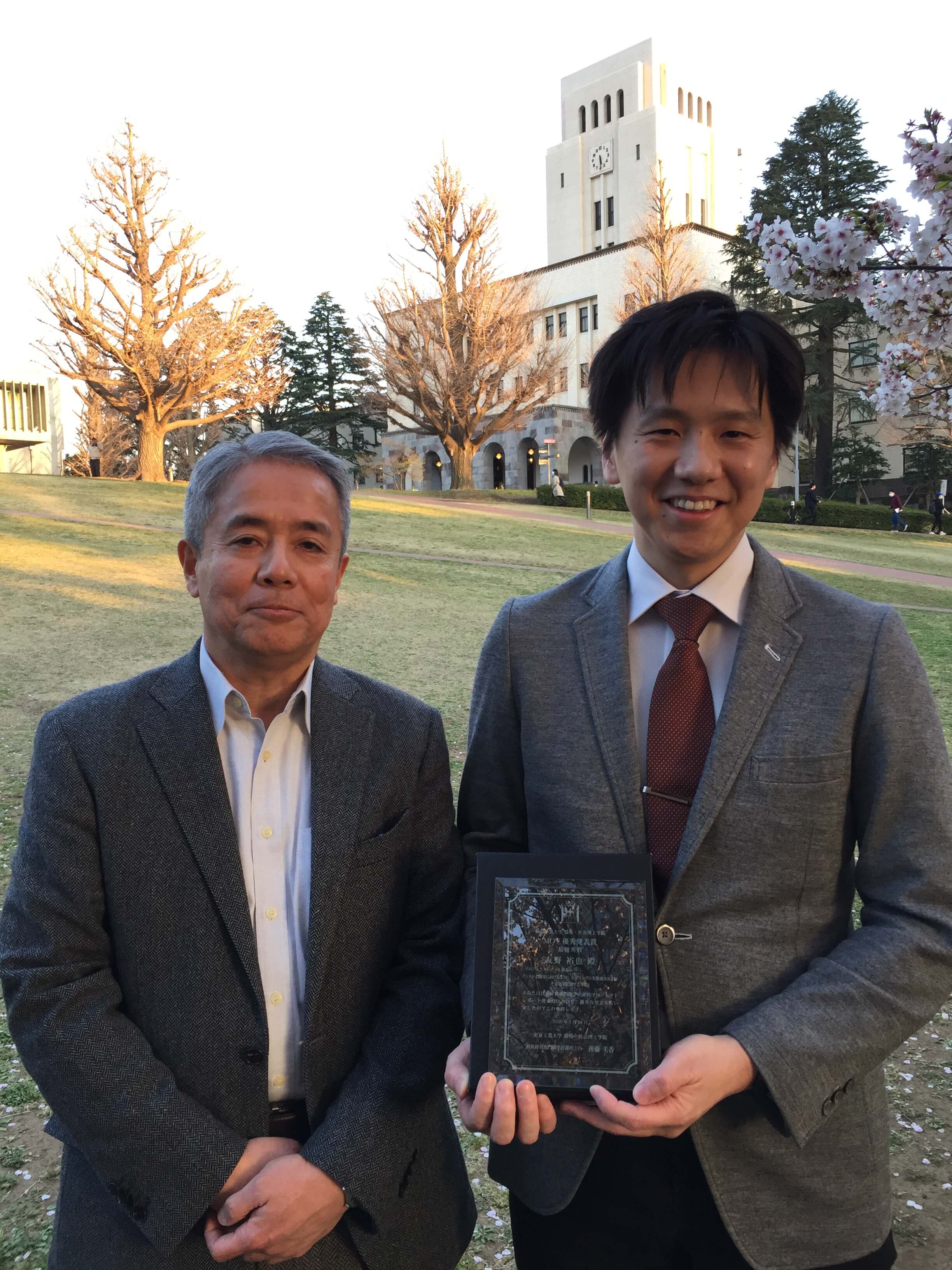【研究状況報告:原口さん】
研究計画の準備として、
【研究状況報告:落合さん】
題名:Aviation After Service Businessの展望
~日本と海外のMROビジネス比較・受委託関係分析~
(タイトルは前回アドバイスにより変更)
いただいたアドバイスは以下のとおり
(日髙先生)
研究の「論理性」がない。
研究の道筋としては
①背景:事実に基づくもの
②課題と目的
③研究方法;目的を達成するために妥当な研究方法であるか?
であるが、③インタビュー手法が①②の目的を達成するための妥当
具体的には、論理的道筋を明確にするためには、②具体的記述とな
・背景/ベースデータに以下を明示すること
-日本のMROビジネスが発展/展開していないという事実を示す
-整備事業の中のAirframe領域のボリュームを示すデータ
・産業界における「オフショア」「リショア」の概念と流れの概要
・インタビュー設計時の注意点についてアドバイスをいただいたい
「インタビューの場合、必ずしも相手の立場や考え方によって必ず